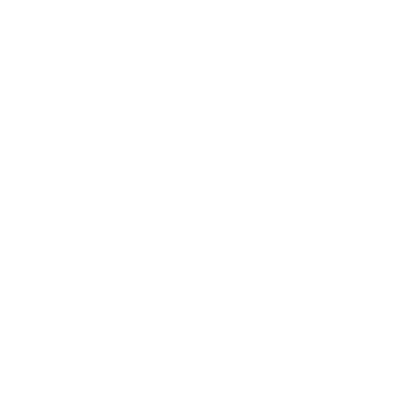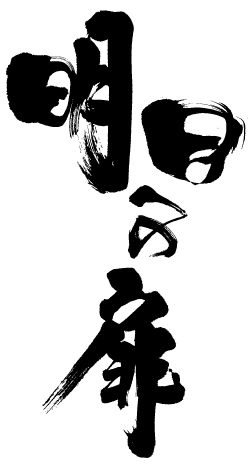動画を見る
全ストーリーへ
動画を見る
全ストーリーへ
 動画を見る
全ストーリーへ
動画を見る
全ストーリーへ
江戸打刃物職人
小沼 亮介
Konuma Ryosuke
1991年 東京都出身
東京都渋谷区出身。子供の頃から野球が好きで、学生時代は野球一筋だった。
高校・大学在学中も、特に職人の世界に興味を持つことはなく、一般企業に就職したが「自分が本当にやりたいと思うことを仕事にしたい」と一年で退職した。
次の仕事を探していたところ「八重樫打刃物製作所」が職場見学を受け付けていることを知り、興味本位で見学を申し込んだ。
親方たちの姿を見て、ものを作ることの面白さに気づき、弟子入りを志願する。それから8年間、地道に経験を積み重ねている。
小沼 亮介さん インタビュー
プロが駆け込む町工場
八重樫で働いていると、本当にいろいろな刃物の発注が来ます。
「包丁」とか「のみ」みたいに聞き馴染みのある道具だけじゃなく、職人さんが「こんな刃物があったらいいんだけど…」と相談に来ることがあるんです。特殊な発注が来た時の親方たちの発想力というか、そういうところがまだ全然追いつけないですね。
「こうしてみなさい」って指示されれば大体のことはできるようになったのですが「見たこともないものを自分一人で考えて作る」、これができないとお客さんからの要望に応えることができないので、経験を積んで引き出しを増やしていきたいです。
160年の歴史を受け継ぐ
先祖代々受け継いで、親方が守ってきた技を受け継ぐのはやはりプレッシャーがあります。
僕は「八重樫打刃物製作所」の見学に来るまで職人って堅苦しくて無口なイメージがありましたが、親方もおじさん(忠夫さん)も本当に優しくて話しやすいです。
最初は何もできませんでしたが、親方たちが丁寧に教えてくださったので今まで続けることができています。
まだまだ目の前の仕事をこなすのでいっぱいいっぱいですが、まずは今の仕事を親方たちと同じぐらいできるようになって認められないといけない、そう思っています。

小沼 亮介さん

八重樫 潤一さん

八重樫 忠夫さん
八重樫打刃物製作所 宗秋 4代目
八重樫 潤一さんインタビュー
今まで家族経営でやってきたので、外から人を入れるっていうことはすごく悩みました。でも小沼くんは本当に真面目に一生懸命やってくれています。職人にはある程度の我慢強さが必要だと思いますが、小沼くんは一つのことを突き詰めてやる我慢強さがあります。それから「10個同じものを作りなさい」と言ったら、本当に10個全く同じにできるような正確さがあります。これは教えたわけではなく、本人の性格のようなものなので、ものづくりには非常に向いているんじゃないかと思いますよ。形を正しく作ることには秀でているんですが、仕上げがまだ少し苦手なようなので、頑張ってほしいところですね。
八重樫打刃物製作所
八重樫 忠夫さんインタビュー
小沼くんは入ってきたその日から「ものづくりは好きだから続くだろうな」とは思ってましたけど、毎日一生懸命がんばってくれています。うちは特に、分業制じゃなくて最初から最後まで作りますから、それも面白いんだろうね。うちの仕事は表に出ないじゃないですか。でも、うちの道具はいろんな一流の仕事を支えてると思うと誇らしいですよ。職人ってのはマニュアルを読んでできるものじゃなくて、教えてもらうのを見て、自分で何回もやって練習して覚えないといけない。彼らが入ってきてからは私が全部やるんじゃなく、どんどんやってもらうようにしてます。
取材を終えて
江戸打ち刃物はまさに日本の手仕事を支える仕事だ。
番組では靴職人と和食料理人に登場していただいたが、お二人ともいかに〝切れる刃物〟が大切か、そして作り手の存在が大切かを語っていた。
八重樫では難しい刃物製作の依頼も断らず受け続けている。小沼さんが江戸打刃物の世界で修業を続けているのも親方や忠夫さんの使命感を肌で感じているからに違いない。
小沼さんの仕事ぶりや言葉の端々に「職人を支える職人」としての自負が見えた。日本の伝統工芸が見直されているとはいえ、それを担う若者は残念ながら少ない。
そうした中で江戸打刃物の世界に飛び込んだ小沼さん。あと数年で一人前の職人になれるだろう。
一人前となった小沼さんの江戸打刃物は、きっと日本の手仕事を支える刃物になるに違いない。

江戸打刃物
江戸時代に、武士が江戸の町に集まると同時に刀鍛冶などの職人も多く集められた。 江戸時代中期になって刀剣の需要が徐々に落ち着いてくると、剃刀や包丁などの刃物を副業として作り出す鍛冶屋が増え、1871年の廃刀令で、鍛冶屋は家庭用・業務用の刃物を作る道具鍛冶への転業を余儀なくされる。 刀鍛冶の技術を受け継ぎ、最高品質の安来鋼を用いたその刃は、切れ味が長持ちし、刃が欠けにくいと言われている。 特に包丁は硬い鋼を軟らかな鉄に合わせることで、無駄な力を逃がし、力を入れずとも切ることができ、多くの料理人が愛用している。